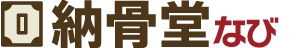大本山成田山久留米分院 平和大仏塔 納骨堂
- train最寄駅
-
ゆふ高原線 久留米駅 / ゆふ高原線 久留米高校前駅 / 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅

\この霊園のお問い合わせはこちら/
霊園概要
所在地
福岡県久留米市上津町1386-22
西鉄久留米駅より西鉄バス[30/31/32/35番]乗車約10分「上津町」下車徒歩約5分
地図
主な施設・設備
駐車場 / 永代供養施設・納骨施設
特徴・ポイント
大本山成田山久留米分院 平和大仏塔 納骨堂は福岡県久留米市にある樹木葬のお墓です。あらかじめ費用、支払い方法などを生前申込ができる霊園になります。ですので、ご家族に負担をかけたくない方にもおすすめです。檀家義務が条件でないことも特徴ですね。また、駐車場があるので自家用車でのアクセスも可能です。ローンでお墓を購入することができるという点も特徴です。
フォトギャラリー
\この霊園のお問い合わせはこちら/
地図・アクセス
令和3年初夏、大本山成田山久留米分院の「平和大仏塔 納骨堂」が令和3年6月23日にオープンしました。
慈母観音像の優しいまなざしの元、世界でも数少ないお釈迦様の遺骨(仏舎利)と共にご先祖様の御霊を末永く安らかにお守りする瑠璃色に輝く納骨堂です。
・遺されるご家族に心配や負担を掛けたくない方
・ご高齢で身寄りの無い方
・菩提寺をお持ちでない方
・遠く離れた故郷のお墓が気になる方
・遠方からご遺骨をお移ししたい方 など
平和大仏塔 納骨堂は、このようなお悩みをお持ちの方におすすめの納骨堂です。
永代供養もお願いできるので、「お墓や納骨堂の後継者」がいらっしゃらない方もでもどうかご安心ください。
《お参りに便利な好立地》
九州自動車道 広川インターから車で約10分、国道3号線から見える慈母観音像が目印です。
広大な駐車場ございますので、お盆やお彼岸の混み合うシーズンも心配ありません。
《見晴らしの良い自然豊かな好環境》
四季折々の花や緑に囲まれ、自然を満喫できる環境の良さが魅力です。
やわらかな陽光、静謐で荘厳な空気が、心に安らぎを与えてくれます。
《お一人、ご夫婦、家族でもご利用可能》
お一人からご夫婦、ご家族まで、様々なタイプの納骨壇をご用意。
ご希望に合わせてお選びいただけます。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
■金剛(こんごう)
仕様:納骨壇 一段式 特別仕様/寸法:幅70㎝×奥行60㎝×高さ220㎝/基数:8基/遺骨収容数(5寸壺)10×4段=40
■胎蔵(たいぞう)
仕様:納骨壇 一段式/寸法:幅50㎝×奥行50㎝×高さ220㎝/基数:14基/遺骨収容数(5寸壺)5×4段=20
■瑠璃 (るり)
仕様:納骨壇 多段式/寸法:幅27㎝×奥行40㎝×高さ23.5㎝/基数:550基/遺骨収容数(5寸壺)2×1段=2
※専用の骨壺購入で6壺入ります。
※鳳凰、蓮華、白蓮は完売となりました。
《お釈迦様の仏舎利と共に供養される》
和大仏塔 納骨堂は、世界でも数少ないお釈迦様の仏舎利と共に眠る納骨堂です。
極楽浄土を彩る七宝のひとつ「瑠璃色」の光が永遠に続く平穏と心からの安寧を表しています。
《永代供養にも対応しています》
納骨堂の継承者は不要です。
遺された方々へのご負担もありません。
お寺が永代に亘って真心込めてご供養いたします。
《檀家にならなくてもご利用いただけます》
宗旨・宗派は不問。檀家になる必要もありません。
どなた様でもご利用いただけます。
日々のお勤めなどは、真言宗の作法にて執り行ないます。